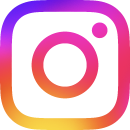TOPページ>光軸調整
ヘッドライトの光軸調整について
郵送でのヘッドライト加工時に光軸調整もしておいて欲しいと言われる事があります。その都度説明させて頂いておりますが、光軸調整はライトを車体に装着した状態でないと正確な調整は出来ないんです。 これは車体の前後の傾きも車体によって個体差があり(サスのへたりや車高調、エアサスのポジションでも変わります)ヘッドライトと車体との相対位置関係もねじ穴の誤差等で微妙に変わります。板金修理した車両であればことさらです。 加工完成時にはヘッドライトの構造から光軸の方向はわかるので、ある程度は合わせておりますが、装着後は必ず微調整が必要になります。加工時にプロジェクターや調整ネジを触らない加工であれば必要はありませんが。 ついでなので調整方法も・・・光軸調整機構の構造は大きく分けて2種類あります。10系アルファードはローとハイで2種類どちらも使っていますので、サンプルにヘッドライト裏側の写真を載せておきます。
まずハイビーム側

このパターンは昔から多いオーソドックスなタイプです。1つが左右用、1つが上下用で完全に役割を分けています。支点は動かない基準部分なので単純に理解出来ますね。そしてロービーム側

このタイプはレベライザーの普及に伴って増えてきたタイプです。レベライザーの動きで上下にプロジェクターを動かす必要があるのでこの様な構造になっていますが、この場合は一応は左右用、上下用と分けられては居ますが、上下を調整すれば左右にも光軸は影響を受けます。このタイプは上下調整時に左右調整用ネジも触る必要が出ますね。あと、調整ネジを回しすぎてネジが抜けたり、或いは破損させる例もたまに発生しています。 調整時には壁に光を当てて、カットラインの位置を見ながらネジを回せば動きがわかりますのでその様なトラブルも回避出来ます。

↑壁に映るカットライン
参考にヘッドライトを分解した写真をどうぞ。このヘッドライトはオデッセイRB1の物です。内部の構造を見ればよりご理解しやすいと思います。

これではちょっとわかりにくいと思いますのでリフレクターを外してみます。

こんな感じです。このヘッドライトはロービームとハイビームが一体になって動くタイプですね。独立しての光軸調整は出来ません。
TOPページへ